「タワーマンションのデメリット」を徹底検証し、「タワーマンション購入を検討している方」がぶち当たる「気になるデメリット」に対する傾向と対策情報を17個ピックアップしました。
更新日:2024年08月07日

イエシルコラム編集部
株式会社リブセンス
IESHIL編集部東京・神奈川・千葉・埼玉の中古マンション価格査定サイトIESHIL(イエシル)。 イエシルには宅建士、FPなど有資格者のイエシルアドバイザーが所属。ネットで調べてわからないことも質問できるイエシル査定サービスを展開しています。イエシルは東証上場企業である株式会社リブセンスが運営しています。

総戸数が500戸、1,000戸といった大規模タワーマンションなどでは、似たような方角・間取りの物件にもかかわらず値付けは様々です。なので、住戸を選ぶ際に「一体どれがお買得物件なのか?」「何を基準に部屋の最適価格を判断したらいいのか?」と分からなくなる人も少なくありません。
新築分譲時の価格設定を読み解けるようになると、この根深い疑問に対する大きなヒントを得ることが出来ます。
そもそも、新築マンションの価格の基になる「値付け」の仕組みについて、あなたはご存知でしょうか?
新築タワーマンションの値付けは、まずはすべての平均価格となる「標準住戸」が設定されます。そして、例えば簡略化して対象マンションが五階建てとするなら、中間の階となる3階フロアの南向け住戸がここでいう「標準住戸」となります。これを基準として、階数と位置によって、値段にプラスマイナスを付けていきます。先ほど挙げた3階フロアの南向きの部屋(標準住戸)を100万円とすると、ひとつ上の4階は110万円。ひとつ下の2階は90万円。3階でも角部屋は105万円。という形で値段が付けられていきます。それぞれの点数差の大きさについては、そのタワーマンションの立地や建物グレードによって異なってきます。
ただいずれにせよ部屋の価格差となる基本的な評価ポイントは以下の様な法則となります。
階数→高層階>低層階(通風、採光、眺望の良さを評価)
配置→角住戸>中住戸(開口部が多さ、通風採光が良さを評価)
向き→南>東>西>北(日当たりが良い順番)
次に、個別ごとの条件によって、さらに価格調整を行います。例えば、地階の住戸なら専用の庭があったり、上層階ならルーフバルコニーが付いているなど、住戸ごとに特別なプラスアルファある場合は、同種住戸よりやや価格をアップ。逆に、2階の住戸で、すぐ下の階がエントランスホールであったり、エレベーターのすぐ前の住戸であったりすると、人通りの騒音などを加味して同種住戸よりやや価格をダウンさせたりします。
他にも、人気の条件を複数満たす住戸には、申し込みが集中しないように、あえて価格を高めに設定したり、逆に不人気の条件を複数満たす住戸には、売れ残らないよう少し大きめのディスカウントを施したりします。このように基本的には、全戸をトータルで見れば均等にバランスが取れるように配慮して価格が設定されているといえるでしょう。なので、この値付が適切であるかぎり、実態価値以上に割り引かれている「お買い得」物件は存在しない事になります。
ただ、あくまで値付の根拠は、過去における注文傾向や販売実績といった社会通念的な価値観に基づくものとなります。ですので、各購入者の価値観と、必ずしも一致するものではありません。例えば、エレベーターまでの距離が煩わしいと考える人にとっては、「エレベーターの目の前の部屋」であっても、個人的には全く気にならないということも十分起きうるといえるでしょう。
(まとめ)→「個人の嗜好と世間一般的な嗜好に差がある場合、当人にとってお得物件となりうる」
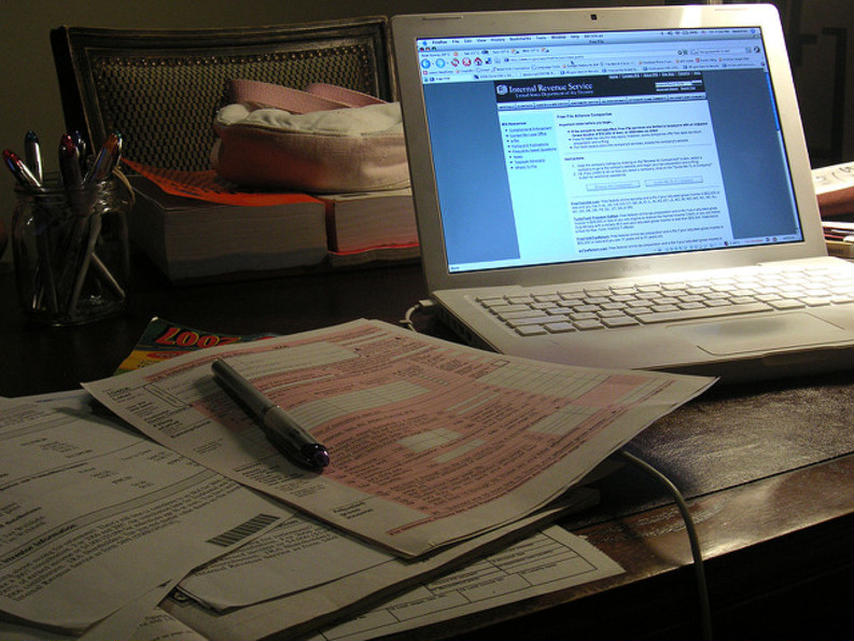
タワーマンションを使った相続税対策について昨今話題になっていますが、そもそもタワーマンション購入することで発生する税金にはどんなものがあるのでしょうか。整理すると、購入後にかかる税金は「固定資産税」「都市計画税」「不動産取得税」の3つとなります。それでは、順番に確認していきましょう。
「固定資産税」
これは不動産絡みで最もポピュラーな税金といえるでしょう。この税金は、土地や家屋の所有者に対して、対象となる固定資産がある市町村が徴収する地方税となります。具体的な税額については、3年おきに見直される固定資産税の評価額がベースとなり、かかる税率は税率は1.4%となります。この税金は、対象となる固定資産を保有している限り、毎年課税され続けます。
「都市計画税」
この税金は、市街化区域内の土地、家屋に対してのみ課せられます。具体的な税額については、前述の固定資産税の評価額に対して、税率0.3%がかけられます。徴収については、固定資産税と一緒に行われます。
「不動産取得税」
これは不動産(土地、建物)の取得者に対し、対象となる不動産がある市町村が徴収する税となります。この税金は、固定資産税のように毎年課税されるわけではなく、不動産を取得した際に「一度だけ」納める税金となります。尚、この税金には特例があり、新築住宅及び中古住宅(木造は築20年以内)の場合で、床面積が50~240㎡以内でかつ、購入者が自身が居住するための不動産であるなら一定額の控除が受けられます。面積が小さすぎたり大きすぎたりしなければ基本的に不動産取得税はかからないケースが多いのが実情です。
そして、ここから更に注意が必要な固定資産税の軽減措置について整理しましょう。
実は固定資産税の軽減措置の違いによって、購入価格が同じ場合、一戸建てよりマンションのほうが固定資産税が高くなります!
詳しくいうと、固定資産税の軽減措置によって、実際の税額は土地部分は6分の1に、建物部分は2分の1になるのです。そのため、物件価格に対する、土地、建物の占める割合次第で、かかってくる税金が変わってきてしまうのです。
平均的なコスト比率を簡略化して例えると、物件価格を100%とした場合、一戸建ては土地70%、建物30%となりますが、マンションは逆に土地30%、建物70%という割合となります。更にタワーマンションでは、狭い土地に高層の建物が建つ訳ですから、土地の持ち分は更に少なく、なおかつ、共有施設が充実させていることも多いため、普通のマンションよりも多額の費用がかかっていることから、土地10%、建物90%という比率となる物件まで存在しています。
シミュレーションすると以下のようになります。評価額が5,000万円の新築一戸建てと新築タワーマンションを比較します。
土地と建物の内訳は
一戸建て マンション
土地:3,500万円 土地: 500万円
建物:1,500万円 建物:4,500万円
となります。そして前述のとおり、固定資産税は軽減措置があり、土地部分は6分の1に、建物部分は2分の1になります
そうすると・・・
一戸建て
土地:3,500万円 × 1/6 = 約583万円
建物:1,500万円 × 1/2 = 750万円
評価額合計: 約1,333万円
マンション
土地: 500万円 × 1/6 = 約 83万円
建物:4500万円 × 1/2 = 2250万円
評価額合計: 約2,333万円
以上の通り、税金の対象となる評価額が新築一戸建てと新築マンションでは大きく異なってきます。
これらの評価額に対して、固定資産税の税率1.4%かけると、一戸建ては約18万円、マンションは約30万円となり、マンションの方が税額は高くなります。
尚、土地評価額を6分の1と軽減措置はずっと変わりませんが、建物評価額を2分の1にする軽減措置については、一戸建てが3年間、マンションは5年間までとなります。従って一戸建ては4年目から、マンションは5年目から固定資産税が高くなることになります。
他にも、マンションの固定資産税が高くなってしまう理由があります。それは、建物に対する減価償却期間の違いで、一戸建ては22年であるのに対して、マンションは47年と設定されています。つまり、マンションは一戸建てより減価償却期間(評価額が減少していく期間)が長いので固定資産税がいつまでも安くならない訳です。ただし、税率に関しては今後の税制改革によって、新築一戸建てと新築マンションに差がつけられなくなってくるかもしれません。
(まとめ)→「今の税制では、戸建てよりタワーマンションの方が固定資産税が高くなる」

前項では、タワーマンション購入後の税金について整理しましたが、税金とは別に必要となってくる修繕積立金についても確認していきましょう。
例えば、都心湾岸エリアに分譲されたあるタワーマンションのケースです。このタワーマンションは、50階を超える超高層で、各住戸は55平方メートルから70平方メートルの面積。価格は6000万円台から7000万円。坪当たり単価300万円を超える高額物件としましょう。このタワーマンションの管理費が1平方メートル当たり216円。修繕積立金は同87円とした場合、70平方メートルの住戸なら戸当たりの管理費が1万5000円、修繕積立金が6000円。2万1000円が月額となります。駐車場代等を合わせて、月々4万円程度と計算することが出来ます。
しかしながら、この4万円という数字にはトラップがあったりします。それつまり、修繕積立金の金額は、新築時が最も安くて、築年数の経過とともに上昇していく仕組みになっているのが一般的なのです。
例えば、新築時は87円でスタートした修繕積立金ですが、5年後に2.5倍の217円、10年後347円、15年後には420円という風にアップしていくのです。これは即ちスタート時の設定額の4.8倍となります。70平方メートルの住戸で6090円が2万9400円にまで高騰してしまうのです。従って、駐車場代等を合わせて、月々4万円程度の負担で住むのは入居当初に過ぎず、15年後には6万円を超える負担が毎月かかってくることが予め決まっているのです。どうしてこういうことが起きるのかというと、タワーマンションを販売するデベロッパーとしては、販売時においては負担額を低く見せることによって、魅力的な価格設定を訴求し可能な限り早く多くの人に売り切りたいという動機が存在するからです。
そもそも、なぜタワーマンションには多額の修繕積立金が必要なのでしょうか。それは、タワーマンション特有の事情があります。例えば、エレベーター一つとっても、超高層建造物であるタワーマンションには、最新の高性能高速エレベーターが必要となりますし、水道水を給水させるポンプも高層階になってくると非常に高性能なものを導入する必要があります。他にも、地震対策としての制振・免震機能や非常用発電機などの設置にも多額の費用を要します。そしてそれらの機器も20年から30年で更新時期を迎えるため買い換える必要が生じます。他にも、タワーマンションは外装工事をするときにも、普通のマンションみたいに足場を組むことができません。
従って、屋上からのゴンドラ作業などを要し、工期が3倍以上かかるともいわれています。これらの理由から、タワーマンションには多額の修繕積立金を積み立てておく必要があるのです。又、これまで建造されたタワーマンションの大半が未だ大規模修繕を迎えておらず、実際に積み立てられている修繕費で賄えるのかどうかも不明なのが実情です。ひょっとしたら今後更に修繕費が増えてしまう可能性もあるので、予め意識しておいたほうがよいでしょう。
(まとめ)→「修繕積立金の金額は、新築時が最も安くて、築年数の経過とともに上昇していく仕組みになっているのが一般的」

最後に、「定期借地権付き」のタワーマンションのメリット、デメリットについて見ていきましょう。
「定期借地権」とは、平成4年に制定された「借地借家法」で生まれた権利となります。通常だと、マンションを購入するということは、土地も建物も「所有する」ことを意味しますが、定期借地権付きマンションの場合は、建物は「所有」するものの、土地は「借りている」状態となるのです。そして、この定期借地権の期間は50年以上という定めがあります。マンションによっては70年といった超超期間で設定されていることもあります。ただし、この期間を過ぎると建物は取り壊し、土地を更地にした上で、地主に土地を返却しなければならない約束となります。
この定期借地権付きマンションは、費用面でも通常マンション等とは異なってきます。まず、購入する際に一時金として支払うべき費用が以下のように増えます、
・保証金
「借地」をするにあたって最初に支払うお金となります。いわゆる「敷金」のイメージで、基本的には土地を返す時に返還される約束となります。
・権利金
数十年も土地を借りさせてもらうことに対しての対価にあたるお金となります。
・解体準備基金(物件によっては無い場合も)
超高層建造物を解体するとなると多額の費用が必要となります。そのために予め購入時にまとめて支払うお金となります。
いかがでしたでしょうか。ここまで17個の気になるポイントを確認してきましたが、これらは比較的ポピュラーで誰もが疑問や不安を感じるものです。しかし、家庭の事情や個人的な事情というのは、人それぞれで千差万別です。それも非常に込み入っていたり、現在進行形の悩みであることも少なくありません。
マンションは一生の買い物ですので、軽率な選択は時として、人生レベルでのダメージを負うことに繋がります。
そこでオススメしたいのが、中立的な立場から自分に最適な物件や業者選びをサポートしてくれる不動産アドバイザーに相談してみることです。イエシルが提供しているイエシルアドバイザーは、不動産売買に詳しい専任アドバイザーが、売買ノウハウから資産運用まで幅広く無料で相談に乗ります。既に多くの無料アドバイス実績がありますので、興味のある方は、コチラをご覧ください。

イエシルコラム編集部
株式会社リブセンス
東京・神奈川・千葉・埼玉の中古マンション価格査定サイトIESHIL(イエシル)。 イエシルには宅建士、FPなど有資格者のイエシルアドバイザーが所属。ネットで調べてわからないことも質問できるイエシル査定サービスを展開しています。イエシルは東証上場企業である株式会社リブセンスが運営しています。



IESHILコラムとは、不動産物件情報に関連してコラム等の関連情報も提供する付随サービスです。
ご利用により、IESHIL利用規約が適用されますので、規約のご確認をお願い致します。